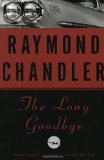
19章の書き出しはこうだ。“I drove back to Hollywood feeling like a short rength of chewed string.”清水訳では「私は車を走らせて、ハリウッドへ戻った」。後半部をあっさり飛ばしている。村上は、その部分を「くたびれ果てた身体で、」と訳している。「噛みしだかれ、短くなった紐のような気分で」と直訳するのが村上流かと思ったが、疲れた気分を表す常套句なのだろうか。
マーロウは今日出会った三人の医者を振り返る。ヴァーリーは裕福だ。危ない橋を渡る理由がない。ヴュカニックについて、清水は「ずいぶん危ない橋を渡っている。看護婦たちは知っているにちがいない」と書いている。原文は“Vukanich was a punk,a highwire performer who hit the main line in his own office.”ハイワイヤー・パフォーマーは、文字通り危ない橋を渡っている。「パンク野郎」も抜けているが、問題は“who”以降だ。ここを訳さないと、危ない橋の意味するものがよく分からない。メイン・ラインは鉄道や道路の本線という意味だが、俗に<麻薬を打つ>幹静脈を意味する(大修館『ジーニアス英和辞典』)。村上の「自分の診療所で自ら麻薬を打っている」が正しい。当時の辞典には載っていなかったのだろうか。
ウェイドは、世界一賢い男ではないが、ヴュカニックに近づくほど愚かではない。となれば残るは、ヴァリンジャー一人。マーロウは、ヴァリンジャーの土地について不動産所有権を扱う会社に勤める知人に電話をかける。しかし会社は終わっていた。探偵も店仕舞いをして食事に出かける。店の名前が“Rudy's bar-B-Q”清水は「ルディーのバー・B・Q」。村上は「ルディーズ・バーベキュー」だ。近頃は日本でもバーベキューのことをBBQと書く。どうしてバーだけ“bar”と書いたんだろう。実は、この店バーとレストランがビロードの綱で仕切ってある。席があくまで、マーロウもバーのスツールに腰掛けてウィスキー・サワーを飲んでいる。「ルディーのバー」と、訳したくなる清水氏の気持ちはよく分かる。でも、やはりここは「バーベキュー」でしょう。
家に帰ったマーロウにウェイド夫人から電話が待っていた。ヴァリンジャーの話に見込みがありそうと感じた夫人にマーロウは、“I could be wetter than a drowned kitten.”と、返している。直訳すれば「溺れた仔猫より濡れているかも」だ。清水は「まだわからんのです」。村上は「全くの見込み違いだったということになるかもしれません」だ。見当が外れたときのみじめな様子の表現に、溺死した仔猫という比喩を持ってくるのが猫好きで知られるチャンドラー流の表現か。日本では「濡れ鼠」というように、ぐっしょり濡れるのはねずみの方だが。“ could be”は、“may be”と同じで、くだけた調子で「たぶん、かもね」の意。清水訳の方がくだけた感じは伝わる気がする。
マーロウは、ヴァリンジャーをもう一度探ることにした。ここでマーロウが用意するのが、“three-cell flashlight”「電池が三つ入っている懐中電灯」(清水)。村上のは「強力な懐中電灯」だが、アメリカ映画でおなじみの握りの細長い銀色の懐中電灯のことだ。清水訳の方がイメージが鮮明。映画字幕で修行した清水氏の訳の方が映像喚起的であるのは当然なのかもしれない。
その一方、同時に用意した拳銃の方は、“The gun was a tough little short-barreled.32 with flat-point cartridges.”を「拳銃は銃身の短い32口径のものだった」(清水)。「小型だが威力のある銃身の短い三二口径、弾丸はフラット・ポイントだ」(村上)と、村上訳の方が原文に忠実。フラット・ポイントというのは弾丸の先端が砲弾型に覆われてなくて、人体に当たるとマッシュルーム状につぶれることで、貫通しにくい。マーロウはアールの狂気をかなり警戒している。
“It took me three quarters of an hour to work up behind the swimming pool and the tennis courts to a spot where I could look down on the main building at the end of the road.”
「プールとテニスコートのうしろをまわって、道の突きあたりの建物を見おろせる地点に出るのに、四十五分かかった。」(清水)
「四十五分ばかりかけてプールとテニスコートの裏側に着いた。そこから道路の突き当たりにある母屋を見通すことができた。」(村上)
原文を読む限り「道の突き当たりにある母屋を見下ろせる地点」=「プールとテニスコートの背後」のはずだ。清水訳だと、その地点がどこなのか分からない。しかし、原文は村上訳のように二つの文に区切らず一文構造になっている。何とか一文で訳すと、次のようになる。
「プールとテニスコートを背に、そこからなら道の突き当たりにある母屋が見下ろせる地点に出るのに四十五分かかった。」(拙訳)
投光器の投げかける光の下で投げ縄の一人遊戯に耽るアールのいでたちをチャンドラーは克明にスケッチする。その中で、シャツの前に垂れ下がる紐の訳が違う。「絹糸を編んだような紐」(清水)。「銀色の編み紐のようなもの」(村上)。原文は“looked like a woven silver code”だから村上訳が正しい。清水氏は“silver”と“silk”を読みまちがえたのではないだろうか。
何かの音に反応したアールが拳銃を構えたのでマーロウは身構えるが、アールはそのまま家の中に入ってしまう。その後の“The light went off,and so did I.”を清水は「灯りが消え、私もそこから姿を消した」。村上は、「明かりが消え、私も身体の力を抜いた」と、訳している。舞台の幕が下りたわけだから、その場を去るのもありだろうし、リラックスすると考えるのもありだろう。こういうところが翻訳家の腕の見せ所なんだろうなあ。
この後、マーロウはロジャー・ウェイドを見つけるのだが、ウェイドとヴァリンジャーの会話が結構長く続く。謝礼として五千ドルを要求する医者に対し、ウェイドは高すぎると相手にしない。
“You have a nasty tongue,Wade.And a nasty mind.”「あなたは下品な口を利く、下品な心の持ち主だ、ウェイド」(村上)というヴァリンジャーに、ウェイドが吐く捨てゼリフ。
“I have a nasty five thousand bucks too, Doc.Try and get it.”を、清水は「だが、五千ドルはここに持っていないよ。とれるものならとってみたまえ」。村上は、「おまけに下品な五千ドルも持っているぜ、ドク。とってみたらどうだ」と訳す。意訳にしても清水の訳では、相手の言葉尻を捉えて皮肉な物言いをするロジャー・ウェイドという作家の嫌味なところがあまり見えてこない。アルコール依存症で娯楽小説を書き散らすロジャーは作家チャンドラーの自意識が濃厚に付されたキャラクターである。ここは、たっぷり嫌味を効かせたいところだ。