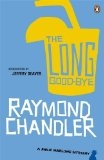
いくらハードボイルド探偵小説といえども、毎回毎回が緊張した事件の連続では、つきあっている読者のほうが疲れてしまう。アントレの後にデザートが くるように、緊張の後には弛緩がほしい。第21章は、一仕事やり終えた次の日、マーロウのどうってことない一日を描く幕間劇だ。
ゆっくりと起き、いつもより多目の朝食を食べたマーロウは事務所を開ける。窓を開け、空気を入れ替えるマーロウの描写の中、汚れのたまってい る場所として“In the corners of the room,in the slats of the venetian blinds.”(部屋の隅っこや、ブラインドの隙間に)に相当する部分が清水訳では抜け落ちている。“the smell of the dust and dinginess”を清水は「空気にこもった塵の匂い」と訳している。匂いはほこりのようにあちこちに分散しようがないから略したのだろう。村上は「ほ こりや、いろんな汚れ」と訳す。清水訳からは“ dinginess”が、村上訳からは“the smell”が抜けている。おあいこというべきか。
相変わらず清水訳に省略が多い。しかし、村上春樹が再訳に乗り出すまで、ミステリ小説に逐語訳が重要視されていただろうか。意味さえ通じれば 意訳でよしとされていたというのが本当のところだろう。むしろテンポのいい訳に人気があった。それは今でも清水訳を好む読者が多いことからも分かる。そう いう意味では、やれ、ここが訳してないとか、トバしてあるとか指摘される清水氏には迷惑な話かもしれない。ただ、考えてみれば新訳の登場によって、旧訳の 再評価も同時になされるわけで、決して悪いことばかりではない。
その日事務所を訪れた依頼人の比喩として用いられた“dingoes who park their brains with their gum”を、「脳みそをおき忘れてきた犬」と清水は訳す。村上によれば「脳みそを糊でかろうじて貼り合わせているぼんくら」。“dingo”は、オースト ラリアの野犬だ。そんなものがアメリカの街をうろついているわけがない。ここは、スラングの<ろくでなし・臆病者>の意だろう。
以下に清水が訳していない部分を記す。( )内は村上訳。
“the potato vine”(つるの絡んだ垣根)
“Tail waggers”(犬猫愛好会)
“That's what makes it I want somebody else”(だから俺としちゃほかの誰かに頼みたかったんだ)
“almost taking the door with him”(危うくドアをはがして持っていくところだった)。
自分の愛犬を毒殺しようとする隣人を見張り、捕まえてほしいというのが最初の依頼だ。ミスタ・クイッセネンがマーロウの皮肉に気づいて怒って部屋を出てゆくところの誇張表現は、そのいかつさをよく表している。こういうところはトバさないでほしかった。
二人目の女性は特に異同はないので略す。三人目のエーデルワイス氏の服装について。
“a purple tie with black diamonds on it”
「紫色のネクタイを結び、黒ダイヤのピンをさしていた」(清水)
「黒いダイヤ柄の紫色のネクタイを締めていた」(村上)
ダイヤモンドの最後にある<s>に注目したい。エーデルワイス氏は金に不自由はしていないようだが、複数のダイヤモンドを散らしたタイピンをさすほどの金満家ではなさそうだ。黒いダイヤ柄の小紋のタイと考えた方が理にかなっている。
それから三日後、アイリーンから電話がかかってくる。カクテル・パーティーへの招待だった。マーロウの応対にアイリーンが一言感想を漏らすところ。
“You sound very solemn today.I guess you take life pretty seriously.”
「今日はとてもまじめなんですね」(清水)
「今日はずいぶんあらたまったしゃべり方をなさるのね。人生をさめた目でごらんになっているのかしら」(村上)
それに対すマーロウの答えは“Now and then.Why?”。「ときには、こんなこともあるんです。ふしぎですか」(清水)。「たまにはそういうこともあります。どうしてですか?」(村上)。 「たまにはそういうこともあります」の後に「どうしてですか?」は、どうだろう。「おかしいですか」とか「いけませんか」ではいけないのだろうか。
テリーからの手紙を読み返していたマーロウは、ヴィクターズでギムレットを飲んでくれ、というテリーの頼みに応えていなかったことを思い出す。ちょうどいい時刻だった。店の前まで来たマーロウは、テリーのしたことを思い出し、車をとめるかどうか躊躇うが、結局とめた。
“He had made a fool of me but he had paid well for the privilege.”
「彼は私を愚か者にしたが、その特権をうるのに充分な金を払っていた」(清水)
「テリーは私を愚かしい立場に置いた。しかし、とても気前よく彼はその代価を支払っていた」(村上)
ここは、清水訳の方が原文に忠実。こういうこともあるから、一概に村上訳の方が逐語訳だとも言えないのだ。旧訳に対し、新訳を立てる場合、同 じ訳者であれば、旧訳をそのまま使えばいいが、ちがう訳者が旧訳の言葉をそのまま使うのは気が引ける。少々回りくどくなってもちがう言葉を探すのだろう。 村上訳には、時折りその苦労が見えるようだ。
さて、この章だが、最後の場面をのぞけば、三人の依頼人の部分は、あってもなくても小説に大きな変化はなさそうだ。自分の中短編から一部分を ピックアップしては長編を作っていくチャンドラーの小説作法から見て、このような「つなぎ」の場面は、中短編として考えたものを長編小説に作り変えるため の必要悪なのかもしれない。
その一方で、三つのアネクドートに見られるテーマは、隣人や同居人が自分を裏切ったり、害をなしたりするという疑惑や、夫婦の一方が相手を裏 切り、失踪するというもので、これは『ロング・グッドバイ』を貫く通奏低音になっている。シェイクスピアの『ハムレット』の中で旅芸人によって演じられる 「ゴンザーゴ殺し」の劇が、『ハムレット』のテーマの反復になっているように、劇中劇の果たす意味合いは結構重いものがある。一見すると、ただのジョイント 部分に見えるこの章も、そういうふうに考えると興味深いものがあるといえよう。